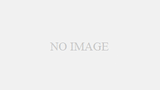日本酒入門。日本酒を好きになるための基礎知識を紹介しよう。
日本酒の「甘口」と「辛口」について
【 辛 口 】
辛口は、スッキリとしてドライな喉越し。
辛口かどうか見分けるためには、ラベルに書いてある「 日本酒度 」を見てみよう。
「マイナス(-)」と「プラス(+)」の表記をみて、マイナスの値が少ないほど甘口、プラスの値が大きいほど辛口と言われている。
【 甘 口 】
甘口は、フルーティーで芳醇な香りで、ふくよかな口当たり。
甘口を探す場合は、マイナスの数字が大きければ大きいほど甘口の傾向が強く、日本酒度が-4以下であれば、甘口と感じる可能性が高い。
3タイプに分かれる特定名称酒 (純米・吟醸・本醸造)
特定名称酒は、「純米系」、「吟醸系」、「本醸造系」に分類できる。
まず、「特定名称酒」は「純米酒かどうか」「原料の米をどのくらい削っているか」という基準で2つに分類できる。
【アルコール添付なし】・・・「純米系」
【アルコール添付あり】・・・「吟醸系」、「本醸系」
日本酒に入れるアルコールとは、醸造アルコールというサイトウキビなどが原料のお酒。
<純米系>
醸造アルコールを使用せず、お米のみを使用しているので、お米本来の味が楽しめる日本酒。
「純米系」は、4種類あり、「特別」がつくもの以外は、精米歩合(せいまいぶあい)というお米の削り度合いによって変化する。精米とは、精米機で、玄米のお米を磨き発芽や糠をとること。
【純米大吟醸】 純米大吟醸は、精米が50%以下の日本酒。
【純米吟醸】 純米吟醸は、精米が60%以下の日本酒。
【特別純米酒】 特別純米酒は、精米が60%以下で、特別な醸造方法で造られている。
【純米酒】 純米は、精米歩合の規定がない。
<吟醸系>
低温でじっくり発酵させることで、酵母にストレスをかけ、吟醸の香りであるフルーティーな味わいになる。
吟醸と大吟醸の違いは、純米系と同じで、精米歩合の比率から呼び方が変わる。
【大吟醸】 大吟醸は、精米が50%以下で、アルコールを添付した日本酒。
【吟醸】 吟醸酒は、精米が60%以下で、アルコールを添付をした日本酒。
<本醸造系>
本醸造は、特別名称酒の中でも、精米の度合いが低いため、価格帯が手ごろな日本酒が多い。
【特別本醸造】 特別本醸造は、精米が70%以下で、アルコールを添付しており、特別な醸造方法で造られている。
【本醸造】 本醸造は、精米が70%以下で、アルコールを添付した日本酒。
熱処理ありか熱処理なしか
【熱処理あり】
熱処理1回のみ:生詰め(なまづめ)、生貯蔵(なまちょぞう)
貯蔵の前の段階で、1回だけ火入れ(ひいれ)をしている日本酒のこと。
火入れをすることで、酵母の働きをストップさせ、品質を安定させ長期保存を可能にする。
【熱処理2回:火入れ】
貯蔵前と瓶詰め前の2回火入れをすること。
火入れを2回繰り返すことで、よりクリアな味わいにすることができる。
この2回の火入れは、主に搾った直後と出荷前に行われ、お酒の味を落ち着かせ、長期保存を可能にする。
【熱処理なし=生酒(なまざけ)】
熱処理(火入れ)を一度もしていない日本酒で、しぼりたてのフレッシュでフルーティーな風味が特徴。
日本酒の品質が変わりやすく、火落ち菌の繁殖を防ぐためにも、冷蔵保存が必須。
<日本酒の出荷の時期>
日本酒の新酒とは、読んで字のごとく「新しく造られたお酒」のこと。一般的には7月1日から翌年の6月30日までの酒造年度内に造られて出荷された日本酒のこと。
出荷の時期によって「新酒」、「古酒」、「熟成酒」と変わる。
【新酒(年度内に出荷されたお酒)】
日本酒の新年度は、7月1日から始まる。
7月1日から翌年の6月30日までを1年とし、この1年の間に醸造、出荷までしたお酒のみ、新酒と呼ぶ。
7月から造り始めるとだいたい1年でもっともお酒の消費が多いという12月と1月に出荷が間に合う。
【古酒(年度越え)】
年度を越えて醸造をした日本酒は古酒と言う。
新酒と同じように半年程度で日本酒を醸造したとしても、7月1日から翌年の6月30日を過ぎてしまうと古酒となる。
【熟成酒】
ワインと同じように長期間保管し、熟成させた日本酒。火入れした日本酒は長期の保存が効くので、熟成することができる。
熟成することにより、味にコクが出て、よりふくよかな味わいを感じることができる。
<日本酒の四季>
【冬〜春】
寒造り(かんづくり):最も酒造りに適した12月から翌年3月頃までの寒い時期に、米の収穫が落ち着いた農閑期に行われる製法を指す。
(新酒) 酒造年度内(7月1日〜翌年6月30日)に造られ、出荷された日本酒」を指す。
【夏】
(夏酒) 夏の暑い時期に適した日本酒です。
夏の暑い時期に「冷やして美味しく」飲める、すっきりとした飲みやすい味わいや、フレッシュな香りを重視したタイプが多い。
【秋】
(ひやおろし) 冬から春に搾った新酒を夏の間に熟成させ、秋に出荷された日本酒のこと。
秋口に出荷する際に2回目の火入れ(加熱殺菌)を行わない「生詰め」の日本酒であることが特徴だ。
<米の種類>
日本酒用のお酒は「酒造好適米」といって、お酒用のお米(酒米)。
普通米と異なり、お米の粒が大きく、お米の中心に「心白(しんぱく)」という荒い組織のタンパク質があるのが特徴。
日本酒用のお酒にも様々な種類があります。
【 山田錦 (やまだにしき) 】
「山田錦(やまだにしき)」は、「酒米の王様」と呼ばれる酒造好適米。
山田錦で造られた日本酒は、雑味が少なく、香り高く、奥行きのある旨味と透明感のあるバランスの取れた繊細な味わいが特徴。
【 五百万石 (ごひゃくまんごく) 】
昭和32年に新潟で開発された酒米です。
五百万石(ごひゃくまんごく)で醸される日本酒は、淡麗でキレの良い辛口の味わいが特徴。
新潟県生まれの酒米であり、新潟の淡麗辛口の酒質を特徴づける重要な酒米とされている。
【 雄町 (おまち) 】
安政6年に岡山で発見された酒米です。
「芳醇なコクと旨味」がある味わい。
栽培が難しく「幻の酒米」とも呼ばれていたが、近年は熱狂的なファン「オマチスト」も存在するらしい。
【 美山錦 (みやまにしき) 】
昭和53年に、長野県で生まれた酒米です。寒さに強いため、東北でも盛んに造られています。
北アルプスに積もる雪のように美しい心白(米の中心の白い部分)を持つことから、美山錦と命名された。
山田錦・五百万石に次ぐ生産量を誇る。硬く溶けにくい性質のため、淡麗でスッキリとした飲みやすい味わいの日本酒に仕上がるのが特徴。
【 出羽燦々(でわさんさん) 】
昭和60年に、山形県で生まれた酒米。美山錦から生まれた酒米なので、寒さに強い特徴がある。
「出羽」は山形県の旧国名「出羽国」に由来し、「燦々」は「太陽が燦々と降り注ぐように輝く」という意味と、山形県に多くある1400m級の山が33座あることにちなんだ「33」の数字を掛け合わせたものと命名されたそう。
柔らかくふくよかな味わいになるのが特徴的な酒米。
< 日本酒の飲み方について >
お酒の温度によって、香りが変化し、その変化を楽しめるのが、日本酒と言われている。
日本酒を温めることを「お燗」と言いうが、料理と合う最適な「お燗」をするには、テクニックが必要だと言われている。
( 熱燗 )
お燗は30度以上に温められた日本酒のことで、5度ずつ6段階に分かれている。
【 日向燗 (30度) 】
常温とほぼ変わらない温度で、常温よりも少し香りが口の中で広がる。熟酒タイプが一番相性がいい温度。
【 人肌燗 (35度) 】
少し温かく感じられる程度で、ふくよかな香りが広がりやすくなる。こちらも熟酒タイプの日本酒がおすすめ。
【 ぬる燗 (40度) 】
熱さを感じるほどではないが、香りがしっかりと出る。お米のふくよかな味を感じられるタイプの日本酒がおすすめ。
【上燗(45度)】
熱燗と呼ばれる温めかたで、一番おすすめの温度。お米のふくよかな味を感じられるタイプの日本酒がおすすめ。
【あつ燗(50度)】
少し熱いと感じるくらいの温度で、すっきりとした辛口になり、香りがシャープになる。
お米のふくよかな味を感じられるタイプの日本酒がおすすめ。
【 飛びきり燗 (55度以上) 】
徳利が熱くなるレベル。辛さが増し、味にキレが増す。お米のふくよかな味を感じられるタイプの日本酒がおすすめ。
( 冷や )
【雪冷え (5度)】
冷蔵庫に一日入れたキンキンの温度。アルコールが抑えられ、すっきりと飲める温度。
香りは立たず、キリっとしたあっさりな味わい。
【 花冷え (10度) 】
冷蔵庫に入っていた日本酒を常温で少しまった状態や冷蔵庫で数時間冷やした状態です。
春に桜が咲く頃の、心地よい冷たさをイメージしており、吟醸酒や大吟醸酒などの繊細な味わいや香りを楽しむのに適している。
【 涼冷え (15度) 】
冷蔵庫から出して少し経ったくらいの温度で、口当たりがよくとろみのある味わい。
日本酒入門まとめ
日本酒について知ると、日本酒を飲むのが楽しくなる。
この日本酒はどこのお米を使っているのか、どの季節に飲もうか、どの温度で飲もうか。○○県の酒米を使っているから、肴も○○県のものにしてみよう、など。
日本酒は温めることで、冷酒や常温とは異なり、香りが広がり、旨味や甘味がふくらむのが特徴で奥が深い。
最後に、「日本酒の生き字引き」とも言われた日本酒業界の重鎮、故・上原浩先生の言葉を紹介しよう。
「酒は純米 燗ならなお良し」